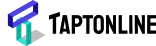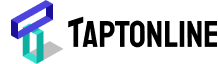東京や横浜などの大都市圏で、火葬場のキャパシティ不足が社会問題として浮上している。亡くなった後すぐに火葬できず、遺族が数日から場合によっては10日以上も待たされる事態が頻発。日本女子大学名誉教授の細川幸一氏は「死亡者数の増加に対し、火葬場の稼働時間や施設数が追いついていない。住民感情を考慮しながらも、運用改善を含めた抜本的な対策が必要だ」と警鐘を鳴らす。
厚生労働省の2024年9月発表データによると、2023年の国内死亡者数は157万6016人と統計開始以来最多を更新。一方で出生数は72万7288人と過去最低を記録し、84万人超の自然減となった。「多死社会」と呼ばれる新たな時代において、終末期インフラである火葬場への需要が急速に高まっている。
実際に横浜市では市営4カ所の火葬場が常時満杯状態で、平均5~6日、最長10日以上の待機期間が発生。この間の遺体保管費用として追加で10万円以上かかるケースも報告されている。「祖父のお通夜後にすぐ火葬できず、冷蔵庫代だけで15万円かかった」(横浜市在住・50代女性)という悲痛な声も上がる。
さらに深刻なのが都市部における料金格差だ。東京23区では都営2カ所に対し民間7カ所という偏在状況で、公営(4~6万円)と民営(8~30万円)に最大7倍以上の開きがある。「都営は3週間先まで予約埋まっているため泣く泣く民間を選んだ」(世田谷区・60代男性)といった経済的負担を強いられる事例が多い。
背景には立地選定の難しさがある。住宅密集地では「景観悪化」などを理由とした住民反対運動により計画頓挫する例が後を絶たず、「死」に関する施設への根強い抵抗感が見て取れる。東京都は自治体向け財政支援制度を創設したものの、「お金より地域理解を得る方が難しい」(都関係者)という本質的課題が残る。
突破口となり得るのが横浜市の事例だ。2026年度供用予定の新施設では工業地域内の公有地活用により反対意見を最小限に抑え、「産業ゾーンなら受け入れやすい」(市担当者)という知見を得ている。
専門家からは即効性のある対策として、(1)現行施設での24時間稼働システム導入(2)休業日の段階的縮小(3)最新式焼却炉による処理能力向上──などの提言が出ている。「今後10年で死亡者数はさらに20%増加すると推計されており(厚労省)、早急な対応なしには『葬送難民』問題へ発展しかねない」(細川氏)。人生最後となる旅立ちのために必要な社会基盤整備について国民的な議論が必要だ。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement